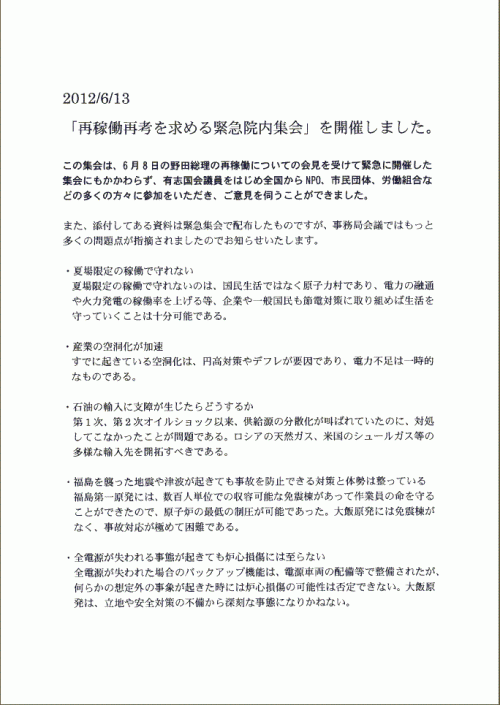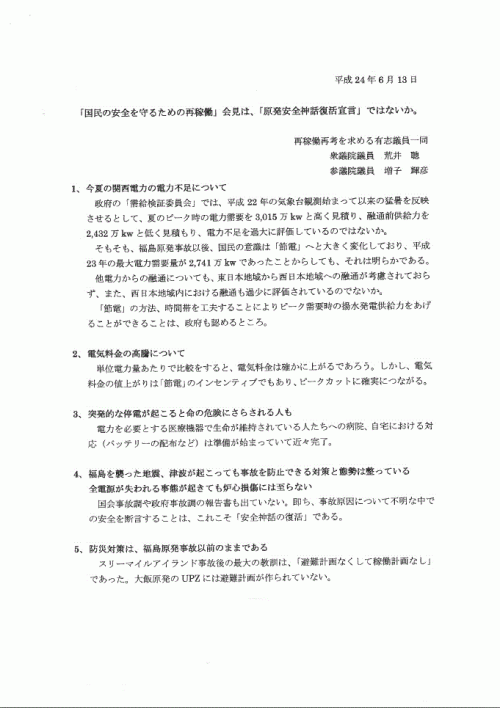子ども・被災者支援法成立への第一歩
掲載日:2012.06.14
今日は、東日本大震災復興特別委員会で子ども・被災者支援法の質疑が行われ、発議 者として答弁をさせて頂きました。委員会室には沢山の被災者の方たちが傍聴に来て 下さり、皆さんが希望の光だと成立を心待ちにしておられるこの法案が参議院で明 日、可決されることを本当に嬉しく思いますし、新たに責任の重さを実感していま す。この議員立法の作成に一から関わった事は、私にとって本当に貴重な経験でした。
子ども・被災者支援法についてPDFにて掲載します。
参議院審議中継のご視聴をご希望の方は、下記のURL(参議院審議中継)より6月14日を選択し「東日本大震災復興特別委員会」をクリックしてください。
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
夕方6時からは、「この時期の消費税大増税に反対する超党派国民集会」が憲政会館 で行われ民主党の多くの心ある国会議員、そして自民党、公明党以外の国会議員が集 結。国民生活が大変厳しい中での大増税は絶対にやめさせなければならないと気持ち を一つにしました。全国から多くの方々が駆けつけ、憲政会館には入れない人たちは 300人を超えました。これが国民の思いです。増税の前にやる事は沢山あります。 政治生命をかけなければならない事が何なのか、私たち民主党が国民から負託された 事は何だったのか、原点に返って考えて欲しい。それが民主党の半数以上の国会議員 の思いです。
先週金曜日の野田総理の「国民の安全を守るための再稼働」への問題点
掲載日:2012.06.14
昨日の「再稼働再考を求める緊急院内集会」の中で、先週金曜日に総理が記者会見で話されていた再稼働の理由が全く納得できないものである、ということを指摘した原発PTのペーパーを配布させて頂きました。 皆さんもご覧になって考えてみてください。
再稼働の再考を求める緊急集会
掲載日:2012.06.13
原発事故収束対策PTが呼びかけ人となり、本日17時30分〜「再稼働の再考を求める院内集会」を開きました。急な呼びかけでしたが全国からたくさんの方々が集まって頂き、静かな雰囲気の中で皆さんから大変に貴重なご意見を頂きました。集会の結びは脱原発アイドルの藤波心ちゃんが、未来を担う子どもたちの代表として心に響く話をしてくれました。皆さん、ありがとうございました!
集会の内容はUSTREAMでライブ中継されていますので、是非ごらんになってください。そして、心ある人たち、どうぞ自分の問題として捉え共に声を上げて下さい。明日、子ども・被災者支援法が復興特別委員会で、質疑の後、採決となります。この法案にしっかりと魂を吹き込んで、被災者の方々の支援が色々な形で広がるように頑張ります!(提案者として、復興特別委員会で答弁します!)
再稼働再考を求める緊急院内集会
掲載日:2012.06.13
民主党原発事故収束対策プロジェクトチーム事務局が中心となって「再稼働再考を求める緊急院内集会」を開催しました。6月8日の野田総理の会見について、今夏の関西電力の電力不足、電気料金の高騰、安全対策、防災対策、事故原因の究明等について、再稼働再考を求める有志議員一同が意見をまとめました。
参加した国会議員が、NOP、市民団体、労働組合などの方々から再稼働や原発の行方などのご意見を受け止めました。
要請
掲載日:2012.06.13
さよなら原発集会
掲載日:2012.06.13
大飯原発再稼働反対院内集会
掲載日:2012.06.13
今日は、再稼働反対の院内集会が開かれます。諦めることなく声を上げ続けることが必要です。国民の皆さんと原発事故収束対策PTのメンバーを中心に国会議員がその気持ちを確認し合いたいと思います。 しかし、地元に週末帰って「真実とは本当に伝わりづらいもの」ということを改めて実感しました。でも私は、自分の思いを曲げることはできませんから、結果を出して理解して頂けるように一生懸命働こうと思っています。街頭演説もやり続けようと思います。少しでも考えてもらう事、気付いて貰う事が大事ですから。
衆議院第5選挙区の中前候補の選対委員会が9日に行われ、懇親会に出席、お話をさせて頂きました。いつ選挙になるかわかりません。党内もどうなるのか、心穏やかでいられない毎日です。
10日は、札幌駅前から街頭演説をしながら定山渓温泉に向かいました。定山渓でJR北海道労組の定期大会が行われ同期の田城議員と一緒にご挨拶をさせて頂きました。JR北海道労組は明確に「原発反対」を訴えています。これからも、国民生活を守るために共に声を上げ続けて頂きたいと思います。原発事故の被害にあわれた方々への様々な支援を法案にした、子ども・被災者支援法が与野党協議で合意できたことはお伝えしましたが、明日の復興特別委員会で質疑が行われ、何とか今週中に参議院で成立できそうな見通しがついてきました。札幌に避難して来ている方々、支援しておられるNPOの方々やお医者さんと、田城議員も一緒にこの法案の説明をさせて頂き、私たちが今何をしたらいいかという事の意見交換をさせて頂きました。2時間以上にわたる、大変貴重な意見交換ありがとうございました。ご要望頂いた事、さっそく動いています。やらなければならないこと、たくさんあります!
要望
掲載日:2012.06.12
北海道長沼町 南長沼地区より「国営農地再編整備事業の計画的な整備と推進に関する要請書」をお受け致しました。
要請に来られた方々
戸川雅光 長沼町長、菊地博 水土里ネットながぬま理事長、永井孝雄 JAながぬま専務理事
原発事故収束対策プロジェクトチーム
掲載日:2012.06.11
環境部門・内閣部門・原発事故収束対策プロジェクトチーム合同会議は、
政府提出の「原子力規制庁」設置法案と自民・公明案の修正協議の進捗状況について説明を受けました。
規制組織の透明性・責任・適格性、緊急時の指示等、修正に向けた議員間協議を行いました。
会議
掲載日:2012.06.08
○環境部門・内閣部門・原発事故収束対策プロジェクトチーム合同会議
いま審議入りしている政府提出の原子力の安全規制を担う新たな組織「原子力規制庁」を設置する法案に、自民・公明から対案が出されてることについて、*既成組織のあり方*緊急時における原子力災害部長(総理)の指示の権限*平時からの防災体制や長期にわたる事後対策*規制の強化*事故の調査や監視の機能等の原子力規制組織制改革に関する主な論点について、野党との修正も含めた協議を行いました。
○経済産業部門・エネルギープロジェクトチーム・原発事故収束対策プロジェクトチーム合同会議
大飯原発3、4号機の再稼働問題で、関係省庁より原子力の安全策及び電力需給の検討状況について、政府側から説明を受けました。
原発再稼働問題について議員間での意見交換を行いました。
安全対策は万全なのか、節電で乗り切れないのか、揚水発電等で対応可能ではないのか、事故原因が判明していない等の意見が出されました。